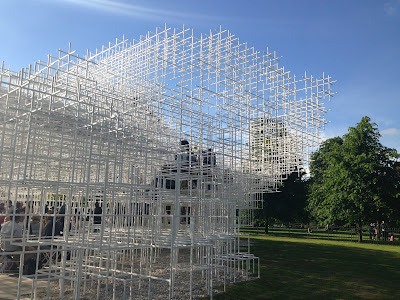3月16日(土)14:30(プレビュー)
アメリカなのに、なのか、それともアメリカだから、なのか。宗教や同性愛、人種といったタブーにここまで踏み込みながら、一方に偏りすぎることなく大団円に持ち込む絶妙のバランス感覚。そして観ている間は、そんな小難しいことを全く考えることなく、ただ思い切り笑い転げることのできる圧倒的なエネルギー。いつもはイギリスびいきの私でも、やっぱりこれだからブロードウェイは凄い、そう素直に思える作品だった。
アメリカで驚異的なまでの人気を博し、2011年のトニー賞9部門を制したモンスター・ミュージカルが、満を持してロンドンはウェスト・エンドに。待ちに待ったトランスファーに、ロンドンのシアターゴーアーたちの興奮はオープニングの数か月前から最高潮に達していた。チケット争奪戦には出遅れたものの、何とかリターンを獲得し、オープニング直前のプレビュー公演を観る。劇場は始まる前からものすごい熱気。(誇張ではなく)酸素が薄く感じられるほどで、音楽が鳴ると同時に一斉に拍手と歓声が沸き上がった。
モルモン教、と言えば、ユタ州ソルトレイクシティに拠点を置くキリスト教系の新興宗教、程度しか知らなかった私は、事前に簡単にいくつかの前知識を仕込んでから観劇に臨んだのだけれど、これらを知ると知らないとでは全く舞台の面白みが変わってくると思うので、以下にいくつか、まとめておく。
・創設者のジョセフ・スミス・ジュニアは預言者モロナイから「ゴールデン・プレート」と呼ばれる書物の存在を告げられる。その書物を掘り出して翻訳したのがモルモン書である。
・宣教師になるには2年間の布教活動が必要。活動の際には2人1組で行動する。
・結婚前の性的行為やコーヒーなどのカフェインを含む飲料摂取は禁じられる。
・決まった下着(ガーメント)を身に着ける。ちなみに白色で、形状はステテコに似ている。
ミュージカル作品としての驚愕するような真新しい要素はないと言えるかもしれない。ただ、徹頭徹尾バカバカしいことを大真面目にやるその姿勢、そしてそのバカバカしい(けれど演じる上では非常に難易度の高い)ことを素晴らしい俳優陣が本気で演じていることが感動的なレベルにまで達しているという点が、典型的なブロードウェイの良作のつくりを踏襲しているように思う。
ごくごく簡単なあらすじは以下の通り。優等生のエルダー・プライスと、彼とパートナーを組むことになる劣等生、エルダー・カニンガムの2人が、(ミッキーマウス好きのプライスがフロリダ州オーランド行きを熱望していたにもかかわらず)アフリカはウガンダで2年間の布教活動を行うことに。しかし貧困やエイズなど、様々な問題に直面しているウガンダの人々にとって、モルモンの教えは絵に描いた餅でしかない。2人よりも先にウガンダにやって来ていたエルダーたちも大苦戦。とにかく一人でもバプタイズ(洗礼)させねばと、破れかぶれになったカニンガムは劣等生ならではの意表をつく行動に出る…。一昔前の西洋諸国による固定概念的なウガンダの人々と、妄信的に一つの宗教を信じている人たちのズレまくりな言動――意図的に明快すぎる描写で笑いを引き出しつつも、最終的にはどの人たちもバカにして終わるのではなく、うまくすくい上げる。だからこそ、一つひとつの場面ではかなり露骨なブラック・ジョークが見られるものの、最後には爽快な気持ちになれるのだろう。
主演の2人、プライスとカニンガムを演じたのは、同役をブロードウェイで演じた経験を持つギャビン・クリール(Gavin Creel)とジャレッド・ガートナー(Jared Gertner)。必ずしもブロードウェイに出ていたから良い、とは言えないけれども、この2人はともにさすがの貫録と実力を見せつけてくれた。クリールは汗を滝のように流しながら、難易度の高い歌を次々と歌い上げつつカチコチの優等生ぶりを発揮。愚かしいまでのまっすぐさに真実味があったおかげで、特に将軍やその部下たちに信仰の素晴らしさを説く「I Believe」は、バカらしくも神々しさすら感じるシーンになっている。ガートナーは外見からしてカニンガムにうってつけ。歌唱力というよりは愛嬌とコミカルな演技で光っていた。先輩エルダーの一人、エルダー・マッキンリーを演じたのは、「ジャージー・ボーイズ」でオリジナルのボブ・ゴーディオだったスティーブン・アッシュフィールド(Stephen Ashfield)。爽やかすぎてどこか胡散臭い笑顔が役柄にピッタリ。そのほか、カニンガムが恋心を抱くウガンダの少女ナバルンギを演じたアレクサ・カディーム(Alexia Khadime)も堂々たる歌声でソロのラストでは拍手喝采を浴びていた。
予想通りというべきか、イギリスでの新聞各紙のレビューは、トニー賞9部門獲得作品としては惨憺たる有様(大多数は星3つ。「デーリー・メール」紙のクエンティン・レッツ氏は「観始めて10分でうんざり」「行く価値なし」と酷評)。こういう、いかにもなブロードウェイらしさを頑なに受け入れないのが(一部の)イギリス人の固さであり、でもだからこそブロードウェイとウェスト・エンドがそれぞれ異なる魅力を持つ作品をつくり出せる所以なのかな、とも思う。ちなみにこうしたレビューもなんのその、同作品の人気が衰える兆しは皆無。それはそれで良いのだが、一点いただけないのが、チケット料金の値上がり率。最近、ウェスト・エンドでは人気作品におけるプレミアム・シート導入(通常、60ポンド台のストールズやドレス・サークルなどの一部を80ポンド台で販売)が目立っているが、同作品ではプレビュー当初は80ポンド台だったプレミアム・シートが現在、一気に127ポンドにまで値上がりしている。いくらなんでもこの短期間でこの値上がり率はあり得ないと思うのだけれど…。